ケルト修道院文化の終焉
「6月8日、異教徒の男たちが、嘆かわしいことだが、リンディスファーンの神の教会を破壊してしまった」
――『アングロサクソン年代記』から
聖パトリックや聖フィニアンらによってキリスト教化されて以降、アイルランドでは氏族制度に密着した独自の修道院文化が花開き、大陸の動乱を逃れてきた大勢のギリシャ・ラテンの学者がアイルランドに古典文学の写本を大量にもたらし、それを修道士たちはつぎつぎと書き写し、後世に伝える橋渡し役をつとめました。また修道士たちはみずから祖国を捨て、カラフを漕ぎ出しては絶海の孤島へ隠遁したり、ヨーロッパ大陸へと赴き「キリストのため」に放浪し、各地につぎつぎとケルト系修道院を設立してゆきました。このような大陸を放浪するケルト修道士のおかげで、はからずも古典文学や教父文学がふたたび大陸へともどされ、ひいては8 - 9世紀のカロリンガ・ルネッサンスの原動力ともなったのでした。フランク王国のカール大帝 (シャルルマーニュ) は自身が文盲だったため、イタリアなど近隣諸国から知識人を付属学校教師として招聘していましたが、とりわけアイルランド人修道士の学識の高さを高く評価していました。カール大帝の宮廷に仕えていたアイルランド人修道士の代表的存在がセドゥリウス・スコトゥス(Sedulius Scotus, 9世紀)、地理学者でもあったディクイル (Dicuil, 生没年不詳) とヨハネス・スコトゥス・エリウゲナ (Johannes Scotus Eriugena, ca.810 - ca.877) です。とくにエリウゲナは博学で知られ、プラトンなどのギリシャ哲学に通暁し、独自の世界観をまとめた大著『自然の区分 (De divisione naturae, ca.867)』はその後の中世の神学・哲学体系に大きな影響を与えました (内容がケルトの汎神論的哲学論考であったため、13世紀にはローマ教皇から焚書命令が出されたりしました)。またこの時代、アイオナ島の聖コルンバの追悼記念として制作されたのが、かの有名な『ケルズの書』です。『リンディスファーンの福音書』とならんで、ケルトキリスト教修道院芸術の極致といえる傑作です。
このようにヨーロッパ大陸各地で華々しく活躍していたケルト修道士たちですが、故国アイルランドでは最大の危機に見舞われていました。ノースメンと呼ばれるヴァイキングの大船団がヘブリディーズ諸島・マン島を経由してアイルランドの海岸へと押し寄せ、上陸してつぎつぎと略奪を開始していたのです。当時のアイルランドは小国分立状態でたがいに相争っていたとはいえ、外国から侵入されたことはありませんでした。ヴァイキングのアイルランド侵入がはじまったのは8世紀末ごろで、その後10世紀ごろまでたびたび大規模な侵入が繰り返されました。ヴァイキングは修道院の宝物庫を狙い、アイルランド各地の大修道院は文字通り修羅場と化しました。彼らは文盲ゆえ貴重な写本にはなんら目もくれず、宝石の象眼された部分のみ引き剥がして戦利品として持ち帰りました。アイルランドに残っていた修道士や領民は必死に抵抗しましたが、しょせん彼らの敵ではありません。ヴァイキングはさらにケリー沖に浮かぶ孤島スケリグ・マイケルの修道院まで襲い、略奪のかぎりを尽くし、当時の修道院長エトガルを身代金目的で連行してしまいました (エトガルはその後獄中で餓死します)。
聖ブレンダンのクロンファートはじめ、5 - 6世紀に設立された修道院はいずれも破壊し尽くされ、灰燼に帰しました。グレンダロッホ、クロンマクノイズ、キルデア、バンゴール、モーヴィルといった大修道院、そして聖パトリックのいたアーマーの聖堂も焼け落ちてしまいます。
このころになると、修道院でも自衛手段として非常時に貴重な写本や自分たちが避難できるように、窓のない円筒形の塔を造りはじめます。それがいまでも各地の修道院遺跡に散見されるラウンドタワーです。
ノースメンの侵攻ルート(出典: 波多野裕造著『物語 アイルランドの歴史』中公新書より)
聖コルンバゆかりのアイオナ島の大修道院も記録に残されているだけでも795年、802年、806年と三度ヴァイキングの略奪を受け、806年の侵入時には修道院長はじめ30人の修道士が殺され、亡骸はそのまま浜に放置されました (いまでも「殉教者の入江」と呼ばれています)。度重なるヴァイキングの攻撃で、ついに修道士たちは最終的にアイオナを放棄、故国アイルランドへと逃れます。そのとき大切に持ち出されたのが、かの『ケルズの書』と伝えられます。しかし故国でもヴァイキングの略奪から守るべく、畑に埋めたりしなければなりませんでした。『ケルズの書』も『リンディスファーンの福音書』も、こうして奇跡的に難を逃れた写本や宝物の一部なのです。
アイルランドに上陸し、各地で略奪を繰り広げていたノースメンたちも、しだいに土着化し、都市を建設しはじめます。ダブリンやウォーターフォード、コーク、リメリックなどはもともとヴァイキングの入植地でした。ヴァイキングはそれまで都市というものをもたなかったアイルランドに本物の都市をつくり、貨幣による交易を活発化させました。11世紀にブライアン・ボルーらによってヴァイキングが撃破され、一時的にアイルランドは統一されはしましたが、各地の修道院にはもはやかつての栄光はなく、その後ノルマン人の侵入や、イングランドの植民地化などで衰退の一途をたどります。
聖ブレンダンの創設したクロンファートの場合、ヴァイキングに破壊されたのち修道院と礼拝堂がロマネスク様式の聖堂として再建され、イングランドが国教会に移行した16世紀ごろまで細々と存続していましたが、その後カトリックへの迫害が強まると放棄され、廃墟と化しました。近年、アイルランド国内でもこのような初期キリスト教修道院の遺構の保存運動が高まり、クロンファートの聖堂も保存措置がとられました。
ケルト修道院文化を衰退させたのは、じつはヴァイキングの来寇だけではありませんでした。聖コルンバが息を引き取る直前の597年4月、イングランドでは遅まきながらローマ教皇直属の宣教師聖オーガスティン (St Augustine of Canterbury, ? - 604 ) がケントのジュート族の王エセルバートをキリスト教へ改宗させました。その後オーガスティンはローマ教皇により初代カンタベリー大司教に任じられます。当時すでに長い布教活動の歴史があったアイオナやアイルランド出身のケルト修道士は、このときはじめてローマ教会と接触します。またヨーロッパ大陸各地を放浪するケルト修道士の活動範囲が広がるにつれ、彼らとローマ教会側に属する大陸の聖職者が衝突することも多くなりました。ケルト教会は異端扱いこそされませんでしたが、もともとローマを経由しない東方教会系の性格をもち、ローマ教皇を頂点とする位階制度は認めつつも大修道院長中心のケルト教会とローマ教皇側の対立はしだいに深まり、ついに決定的な亀裂を生じます。ここで槍玉に挙げられたのは復活祭を祝う日付けの食い違いと、ケルト修道士の奇妙なトンスラ (剃髪) でした。
とくに復活祭の日付け問題は規律上の問題ではなく信仰上の問題という観点から重要視され、これをめぐってバー Birr 近郊のマー・レナ Mag Lena (629年または630年) とウィットビー Whitby (664年) で宗教会議が開かれ、マー・レナ会議以後、マンスターなど南部教会のみがローマ方式の受け入れを同意。二度目のウィットビー宗教会議のとき、主宰者ノーサンブリア王オズウィ Oswiu は、「使徒ペトロの後継者たるローマの主張が正しい」として頑なにアイルランドの伝統を守ったアイオナなどケルト系北部教会の主張を退けてローマ方式採用を決定しましたが、これは事実上、ケルト教会がローマ化を受け入れたものでした。北部教会も加わってローマ方式を全会一致で認めたのは697年バーにおける会議でした。ただしアイオナ共同体のみケルト方式に固執したために716年、アイルランド在住のアングロ・サクソン人司教エグバート Ecgberht が説得し、アイオナも最終的に譲歩してローマ方式を採用しました。このように全ケルト教会がローマ方式による復活祭の日付けを採用するまで、おおよそ100年かかりました。
ローマ教会側との一連の「復活祭論争」以降、ケルト教会側の求心力は急速に弱まってゆきます。度重なるヴァイキングの襲来ともあいまり、かつてのような放浪する修道士たちも姿を消し、彼らが大陸各地に創設したケルト系修道院も、ベネディクト会則の普及とともに力をつけたクリュニー会などの定住型大修道院に取って代わられてゆきました。時代はローマ教皇を中心とする中央集権的なカトリック教会が支配する世界となり、独自性を失ったケルト教会はローマカトリック側に吸収されてゆきます。
大陸での動乱により花開いたアイルランドのケルト修道院文化でしたが、皮肉なことに大陸での混乱が収まり、ローマを中心としたあらたな社会体制と教会制度が確立されると、その役目を終えることになりました。しかし彼らが大陸各地を放浪し、つぎつぎと修道院を建て、ギリシャ・ラテンの古典や教父文学の写本を制作したからこそ、中世ヨーロッパの文化は救われたのです。
大修道院刷新運動ケーリ・デと『航海』ブレンダンは「アイルランド12使徒」のひとりに数えられ、アイルランド教会特有の修道院制の礎を築いた聖人のひとりです。しかしながらその後もアイルランドの政治状況はあいかわらず100以上の小国に分立、「上王 (ハイキング)」という地位こそあったものの、事実上まとまった統一国家などもなく、部族間抗争が絶えることはありませんでした。一氏族は事実上、そのまま一修道院共同体を形成していました。7世紀になると、聖職者としての叙階さえ受けていない氏族の長が大修道院長を兼任することも珍しくなくなり、富と権力が大修道院共同体に集中するようになります。そのため修道院どうしが氏族間抗争に巻きこまれ、修道院長が殺害されたり、教会が破壊されるといった事態も珍しくなくなりました。かつては多くの人の崇敬を集めていたアイルランドの大修道院共同体もこうして堕落し、世俗化していきました。 この「堕落した霊性」を救おうという刷新運動が8世紀前半、リズモアやダリニシなど南部教会を中心にしてはじまります。やがてこの霊性刷新運動はメイルルアン (Máelruain, d.792) やドゥブリティール (Dublittir, d.796) らがフィングラスやタラハトの修道院を中心にして発展させてゆきます。彼らは自分たちのことを「神の僕」を意味するラテン語 Cele De をそのままアイルランドゲール語化した「ケーリ・デ Céli Dé」と自称したことから、これら一連の改革運動は「ケーリ・デの教会刷新運動」と呼ばれ、世俗化した修道院を霊的側面から再建しようとする運動でした(同時期、大陸でも同様な霊性刷新運動があったこととの関連性についても指摘されています)。 彼らは徹底的な禁欲主義を主張し、修道院教会における典礼や『聖パトリックの法 (734年制定)』、『贖罪規定書 (780年)』の遵守などを徹底させました。また聖職者にたいしては当時の慣習法ブレホン以上に厳格な規律を課し、聖性を再生させようと試みました。またブレンダン時代とは逆に、過激な「贖罪巡礼」を戒め、隠修士・修道士がアイルランド国外へ出ることを禁じ、また修道院の肥大化した富にたいしては私有財産の放棄を求めました。 こうした時代背景が『航海』にも反映しています。現存する最古の写本は10世紀に大陸で製作されたものですが、その祖形になった物語はちょうどこの「ケーリ・デ」時代の産物です。そして「ケーリ・デ」の運動から、ラテン語やゲール語で綴られた中世アイルランド修道院文学がつぎつぎと産み出されていきました。この時代の筆写士(scribe)の地位は、いわばかつてのフィリのような教師・知識階級として平信徒の信望を集めるほど高いものでした。この霊性刷新運動時代に編まれた代表作としては『アイルランド聖人禄』(c.750)、現存する最古の聖人暦『ケーリ・デ、オエングスの聖人暦』(c.793-820)、そして「ケルト美術展」にも出品された『ストウのミサ典礼書』(c.A.D.792-803)などが挙げられます。『アイルランド来寇の書』など、ケルト色の濃い伝承も直接の作者は彼らケーリ・デの影響を受けた筆写士たちなのです。 こうして霊的にみごとな再生 (ルネッサンス) を成し遂げたかに見えたアイルランドのケルト修道院でしたが、「東方人 (オストマニ)」を自称するヴァイキングの襲来には無力でした。『航海』28章で出てくる終末論的な科白はじつはこのヴァイキング襲来のことを暗示しているとも言われます。度重なるヴァイキングの修道院襲撃により、830年以降はこの「ケーリ・デ」運動も下火になり、ついにはアイルランド修道院の黄金時代そのものも10世紀には終焉を迎えることになります。 |
| ←Back | Top | Next→ |
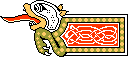 |
 |
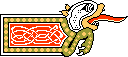 |