ケルト航海譚「イムラヴァ immrama」について
キリスト教以前からドルイドやフィリが代々口承で語り継いできた古代ケルト神話は、ケルトの修道士たちによってはじめて文字文学として記録されました。アイルランドは一滴の血も流さずにキリスト教化された唯一の例ですが、それはおそらく自分たちの祖先から受け継いできた遺産をけっしておろそかにせず、うまくキリスト教に同化させていった結果と言えるでしょう。
ここで問題なのは、現在わたしたちが目にするケルト神話群はどこまでオリジナルの原形をとどめているか、です。
彼ら写字生にとって、筆写する原本に忠実であることよりも原作にどれだけキリスト教的要素を織り交ぜ、自分たちの祖先が野蛮な異教徒ではなく正当なアダムの子孫であると主張することのほうが重要でした(『アイルランド来寇の書』などがその好例です)。ただ、そのブレンドのさじ加減はたいへん微妙なため、筆写したケルト神話までギリシャ・ラテンの古典、北欧・東方神話を下敷きにした「写字生の創作」に近い性格のものなのか、それともまぎれもなくドルイドらによって伝承された物語にキリスト教的脚色を加えたものなのかについては膨大な研究の蓄積があるにもかかわらず、いまだ意見の一致が見られていないのが現状です。
以上を前提としたうえで、ケルト修道士たちの書き残したケルト航海譚について、若干の考察を記してみます。
ケルト修道士の書き残した古代アイルランド神話群には英雄物語や冒険物語が多く含まれていますが、そのなかには冒険譚 (echtrae , 複数形はechtrai) と航海譚 (immram, 複数形はimmrama)というジャンルがあります。現在写本が残されている冒険譚には『コンラの冒険』、『ネラの冒険』、『レヘリの冒険』などが知られています。これらの主要テーマは主人公が生きながら超自然の世界へ赴き、さまざまな冒険をへて帰還するというものです。
いっぽう航海譚のほうは、アイルランドの地理的条件が色濃く反映された物語で、当時の船乗り修道士の体験談なども織り交ぜながら、キリスト教色を前面に押し出した作品が多いことが特徴です。こちらもやはり主人公がなんらかのきっかけ、もしくは啓示を受けて、西の海に浮かぶ「地上楽園」をふくむ島々をめぐり、帰還する筋立てで一致しています。『聖ブレンダンの航海』以外で現存するのは『メルドゥーンの航海』、『スネーフサとマックリアグラの航海』、その異版の『聖コルンバの聖職者の航海』、『コラの息子たちの航海』、『ブランの航海』です(『ブランの航海』については冒険譚として分類する研究者もいます)。このうち『ブランの航海』がもっとも古く、成立したのは7世紀後半から8世紀初頭と言われています。またこれらケルト航海譚はすべて修道士らのカラフによる航海体験そのものを綴り、文学としてキリスト教的に昇華させたものととらえる研究者もいます。また冒険譚とくらべると、異界へたどりつくことよりも、「航海の顛末」に重点をおいた書き方になっていると指摘する学者もいます(ドロシー・アン・ブレイなど)。
イムラヴァ immramaの語源は古アイルランドゲール語で「漕ぎまわる」という意味で、文字通りアイルランドならではの海を舞台とした物語です。これらの現存する航海譚の原型がキリスト教化されたあとも生き残ったフィリたちによって口承され、ケルト修道士たちがそれにキリスト教色を追加して記録したものと思われますが、なかには完全に修道士の創作、もしくは『聖ブレンダンの航海』のプロトタイプとなった物語を書き直したとおぼしきものもあり、写本どうしの相関関係や系譜もまだ完全には解明されていません。
19世紀の創作と言われる『常若の国オシーンの物語詩』はイェイツによる叙事詩にまで発展したものですが、このなかに登場する「常若の国 Thír na nÓg 」はキリスト教化された航海譚にも、いわば常套手段として登場する重要な構成要素です。西の海の沖に浮かぶこの「地上の楽園」には生老病死はなく、わが国の「西方浄土」にきわめて近い思想です。ただ、この一見ケルトの専売特許と思われる「常若の国」ですが、これは世界各地の神話伝承に見られる題材でもあり(アトランティス、エル・ドラド、エデンの園など。紀元前50年ごろ、ギリシャの地理学者ストラボンは現在のカナリア諸島付近に「幸福諸島」があるとの記録を残しています)、はたしてほんとうに古代ケルト伝来の思想なのかどうかはやや疑問です。
ともあれ、きわめてユニークな文学ジャンルであるアイルランドの航海譚は、『聖ブレンダンの航海』がなければ、完全に忘れ去られてしまったかもしれません。その点でも『聖ブレンダンの航海』の功績は無視できません。
また『聖ブレンダンの航海』と『メルドゥーンの航海』は兄弟のような関係にあると言えます。三人のよそ者が乗船し、三人とも帰還できないこと、「鍛冶屋の島」や海にそそりたつ「水晶の柱」など共通項が多く、最新の研究ではメルドゥーンの原型となった航海譚からラテン語版『聖ブレンダンの航海』とおなじくラテン語版『メルドゥーンの航海』がそれぞれ成立したと言われています。1
1. くわしくはつぎの箇所を参照してください。
Clara Strijbosch, The Seafaring Saint, October 2000, Four Courts Press, Dublin, pp. 163-65.
革舟カラフCurraghについて
アイルランド古代伝承とヨーロッパ大陸の古典文学 とを一体化させたケルト特有の航海物語に登場する舟とは、たいていの場合はカラフcurragh, currach(クレア・ケリー地方ではnaomhóg[発音はニーヴォーグ、ラテン語navis+óg< = small craft>に由来する古アイルランド語から。複数形naomhóga。ディングル半島では単純にcanoeと呼ばれる)を指します。
カラフとは古アイルランドゲール語で文字通り舟を意味します。これは船舶史上最古のタイプである獣皮船の仲間で、イヌイットのカヤックやウミアクと同様、船体の木枠に動物の皮を張った舟の一種です。ただしカヤックやウミアクがたんに生皮を舟の木枠に張っただけなのにたいし、アイルランドのカラフはきちんとなめし加工を施した獣皮(おもに牛革)を船体に張っている点が大きく異なります。革舟カラフの記録は古くはギリシャの地理学者ストラボン、ローマのカエサル、ソリヌス、プリニウス、ルカヌスらの著作に見られます。カエサルの記録によれば彼はブリテン島の島民が使っていた革舟にヒントを得て部下に革製の水陸両用船を造らせていますし、プリニウスも彼らが革舟で海峡を横断して錫交易をおこなっていたことに言及しています。このことからして、紀元前よりアイルランドやブリテン諸島ではこれら革舟がひろく使われていたことは明らかです。また英国の船舶史研究家ポール・ジョンストンの実地調査にもとづく論考によれば、革舟の歴史は巨石文化時代、ひいては中石器時代にまで遡ります。
現在でもこのカラフは現役漁船としてアイルランド西海岸一帯、アラン諸島などで使われています。見かけによらず時化に強く、かつては牛や羊の運搬にも使われていました。ただし船体は現在では牛の革にかわり防水用タールを塗りつけた帆布(カンヴァス)か、グラスファイバーが使われています(最近は損傷しやすい帆布よりも丈夫なグラスファイバーが主流です)。船体の大きさは昔のカラフは全長36フィートほどで、セイルも備えていました。現在は4,5人乗り型が一般的で、船体も小ぶりで全長15フィートほどですが、構造じたいは聖ブレンダンの活躍していた時代とあまり変化していません。
聖コルンバがアイオナへ船出したのもこのカラフですし、聖ブレンダンもカラフを駆ってウェールズやブルターニュ、オークニー諸島、シェットランド諸島へ渡ったと伝えられています。賢者アリ作と伝えられる『アイスランド植民の書 Landnámabok』にも、アイスランドにこのような革舟に乗ってアイルランド(「西の国」と書かれています)から隠者がヴァイキング入植前にすでにやってきていたことが記録されています。
ただし、ラテン語版『航海』に先駆けて750年ごろ成立したといわれる『聖ブレンダン伝』では聖ブレンダンが「約束の地」を求めて二度にわたって航海したことが書かれていますが、二度目の航海のときに使用した舟はカラフではなく「60人乗りの木の大船」を造らせて船出したとあります。最初の7年にもおよぶ航海が徒労に帰して故国へ帰還したとき、聖ブレンダンは養母聖イタを訪ねます。聖イタはブレンダンに、動物の血を流して作った革舟では目指すかの地へはたどり着けまい、そこは一度たりとも血で汚されたことはなかったのだからと諭します。当時のアイルランド西海岸に大型船を作れるだけの木材があったかどうかは疑問です。そもそもカラフは木造船が作りにくい土地柄で発達した船舶ですので、これはおそらく象徴的な意味で使われたのだろうと思われます。当時のアイルランド・ブリテン諸島では革舟カラフによる航海がもっとも一般的だったのです。
参考リンク:ジェイムズ・ホーネルによる「アイルランドのカラフ」論考(一部、PDFファイル)

コネマラ地方のカラフ
Courtesy of ©Tim Connor, Not Dot Com Pictures.
ケリー州マハリーズ半島のカラフ造りを紹介した動画クリップ。
| ←Back | Top | Next→ |
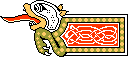 |
 |
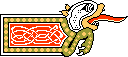 |